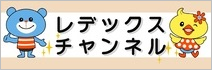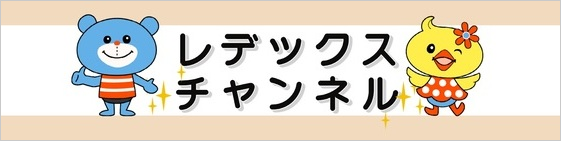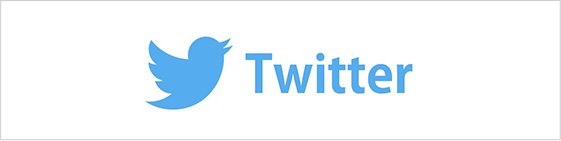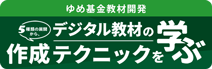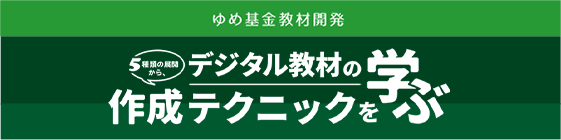■ 連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ(最終回)
■□ 連載:発達障害があると疲れやすいって本当?:ASDと疲労の関連
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ(最終回)第3回 求めることは、与えること
───────────────────────────────────…‥・
前回の記事で私は、「言われたことを一瞬でイラストに変えてくれるアプリが、私たちのコミュニケーションにどのような価値をもたらすか」について語りました。今回の記事では「このアプリを入り口として私たちが目指す社会」について、もう少し詳しく書かせていただこうと思います。
■ 「3階に行く」のは「階段を上がる」より難しい
「階段を、上がるよ……」
お母さまが息子さんに促すと、廊下で戸惑っていたご様子の息子さんが、階段をトコトコと上り始めました。私が
「3階に、行こう」
と、検査のご案内をした直後の出来事でした。
「うちの子、この歳ですけど……まだ数の大小とか、階の概念とか、ちょっと難しいみたいなんです……でも、階段を上がるとか降りるとか言えば、通じるので……」
と、お母さまが少し恥ずかしそうに仰いました。
私は、強い衝撃を受けました。少し屈んで、目の高さを合わせ、「やさしい」表現で男の子に話しかけた「つもり」になっていた私の言葉は、彼にとっては決して「やさしい」ものではなかったということに、私はその瞬間まで、全く気づけていなかったのです。
※ 「3階に行く」ことと、「階段を上がる」ことの違いを表すイラスト
たしかに、あらためて考えてみれば「3階に行く」と「階段を上がる」の間には、無数の分岐があります。
東大の小児科外来(2階)から向かうなら、3階は「上がる」べき場所ですが、精神科外来(4階)から向かうなら、3階は「下がる」べき場所になります。更に離れた階からなら、階段よりエレベーターを使う方が適切でしょう。
つまり「3階に行こう」と言われて「階段を上がる」ためには、少なくとも、極めて抽象的な「階」という概念が分かり、いま自分が居るのが「2階」であると分かり、目的地の「3階」は「2階」より「上」であることが分かり、「3階」と「2階」は「1階分しか離れていない」から「エレベーターより階段がいい」と分からなければならなかったわけです。
ところが、30年以上も生きてきた小児科専門医の私は、その瞬間まで「3階に行く」という表現の持つ難しさに、(恥ずかしながら)全く無頓着だったのでした。
小児科の診察室では、こんなことが日常的に起こります。
当たり前に「階」の概念を獲得し、当たり前に「数の大小」を理解し、当たり前に「移動手段」の状況判断ができる私たちにとって、「3階に行く」という言葉がけの難易度を想像しようと試みることは、とても難しいと、私は(自分自身への反省も込めて)思うのです。
■ 叡智は、現場にある
どのような声掛けが通じるか、どのようなイラストがお子さんに好まれるか、どのような態度がお子さんの将来にとって望ましいか……試行錯誤の結果として蓄積される生活のノウハウは、病院の中ではなく、問題と対峙している子育て現場にあります。
「3階に行こう」がお子さんにとって難しいと気づき、「階段を上がる」に言い換えて問題を解決する、あのお母さまのような「大発見」に、私はこれまで数々の衝撃を受けてきましたし、おそらく私がまだ接することができていない「大発見」も、世の中には無数に埋もれているのでしょう。
医学や医療は、私たち人類が過去に行った無数の試行錯誤と、その結果として発見された「効果的な介入」の寄せ集めです。
※ 江戸と昭和と令和の医学研究を並べたイラスト
江戸時代、葛の根っこが風邪に役立つから、医療者は薬草園にたくさんの植物を集め、埋もれていた植物から数々の漢方薬を調合し、多くの方々に役立てました。
昭和の時代、アオカビが細菌感染症に役立つから、医療者は実験室にたくさんの微生物を集め、埋もれていた微生物から数々の抗生物質を発見し、多くの方々に役立てました。
令和の時代、発達障害の方々に役立つのは、子育て現場で日々実践されるノウハウです。治療ガイドライン(医療者向けに、望ましい治療のあり方を示した指針)にも、発達障害の方々に対しては、環境調整が極めて重要だと書かれています。つまり、子育て現場に埋もれている数々のノウハウを集め、たくさんの患者さんたちに役立てるシステムを、私たちは必要としているのです。
ほんの少し前まで、そのようなシステムを構築することは、夢物語でした。しかし、人工知能(AI)が発達した今ならば、それは夢物語ではありません。
■ 「こどもめせん」の開発サイクル
こどもめせんのアプリでは、そのようなシステムの第一歩として、利用者の方々からメールでフィードバックをいただいています。どのようなイラストが必要か、どのような声掛けが通じたか……といったノウハウが、日々現場から大量に寄せられ、それをもとに1-2週間に1回ずつ、AIはアップデートを重ねているのです。
2025年 7月 14日に、783 枚のイラストを搭載して公開した、こどもめせんのAIは、この原稿を書いている今 (2025年9月14日) 現在、1,565 枚のイラストを搭載しています。AIを試し、フィードバックをくださる78名の方々のおかげで、わずか2か月の間にイラストが2倍になりました。
例1) 紐通し
例えば、お子さんの手指巧緻性向上訓練(指先を器用に動かす練習)に取り組んでおられる作業療法士さんから、「紐通し」のイラストが欲しいとリクエストをいただいたことがあります。
「紐通し」という語は、決して一般的な子供向け辞書に載っているものではありません。私が一人で開発をしている限り、AIへ教えられることなど望むべくもない語彙だったでしょう。私はリクエストに感謝しつつ、次のようなイラストをアプリに搭載しました。
※ 紐通しをしている男の子のイラスト

必要十分なシンプルさで、穴の開いたビーズを紐に通している男の子のイラスト――それなりによい出来と自負していたつもりですが、反響は
「うまく通じませんでした。指先を拡大したイラストはありませんか?」
というものでした。
言われてみれば、なるほど。先ほどのイラストは、お子さんが「紐通し」のときに見ている景色とは違うわけです。(これも全然、当初の私が想像もしていなかったことでした!)
そこで私は、以下のイラストを、追加でアプリに搭載しました。
※ 紐通しをしている手元のイラスト
今度はお子さんの見た通り、ビーズを穴に通す様子が分かりやすいはず……そう思って反響を待つと
「うまく真似してもらうことが、できませんでした。左右、逆になりませんか? 彼は左利きです」
というお返事! ここでも、右利きとして生きてきた私が、左利きの方々に対して想像不十分であったことを、思い知らされる結果となりました。
三度目の正直とばかりに、反転したイラストを追加して、
※ 紐通しをしている手元のイラスト
ようやく
「通じました」
というお返事があり……結果として、いまのアプリに「紐通しをするよ」と話しかけると、以下4種類のイラストが表示されるようになっています。
※ 「紐通し」という語に関連づいた4種類の表示
このようなやりとりを繰り返しながらアプリを推敲していくことは大変なプロセスですが、リクエストをいただくたびに利用者の方々の目線に近づける感覚があり、とてもやりがいのある作業です。
つい先日も、別の施設に勤務されている作業療法士さんから「ひも通しのイラスト……しかも左利きの子の手元のイラストがあるんですね。まさに、こういうイラストがほしかったんです。すごく役立ちます」と、感動のコメントを頂戴しました。
これは間違いなく、最初にリクエストをくださった作業療法士さんと、最初のイラストでは分かりにくいと教えてくれた彼の、おかげです。
例2) 2階へ上がろう
もう一つだけ、具体例を挙げましょう。
数週間前、とある親御さんから「2階へ上がろう」というイラストのリクエストが届きました。
私はあの日、東大病院の2階で、あのお母さまに気づかせていただいたことを思い出しながら、「『~階』という表現に対して、移動手段で言い直すよう促すコメント」と、「階段を上る男の子のイラスト」を準備しました。
※ 『~階』という表現を用いた場合のヒント画面と、階段を上る男の子のイラスト
結果は、劇的だったようです。
「昨夜息子に見せましたら、スムーズに2階へ上がることができました!」
と、お母さまから「!」付きで喜びのメールが届いたとき、私はこの共創システムが、機能し始めていることを実感しました。
あの日、東大病院の2階でシェアしていただいたお母さまの叡智が、時間と空間を越えて、別のご家族を助けたわけです。
■ 求めることは、与えること
これまでAIを研究してきた私には、分かります。今は私が行っている、リクエストメールの仕分けや、プログラムのアップデートも、近い将来AIが行い、数百万・数千万件のリクエストを基に、不断なく叡智をアップデートしていけるようになります。
どんなイラストが必要か、どんな声掛けが望ましいか……現場で何が問題になり、それをどう解決していくことができるのか……一つ一つのノウハウを、集め、共有し、ともに育つ未来を、私たちは創ることができるのです。
そのような世の中においては「助けを求める人」と「助けを与える人」という区別が、消失します。数週間前、2階に上がれなかった男の子を助けたのは、数年前「3階に行くよ」という指示では動けなかったお子さんです。数日前、紐通しできなかった女の子を助けたのは、数週間前「右利きの子のイラスト」では紐通しができなかったお子さんなのです。
困りごとを伝えること、イラストをリクエストすること、アドバイスを請うこと……このような、今まで「求める」行為とされてきたものが、時間や空間を超越するAIと結びつくことで、誰かに「与える」行為となります。求めよ、さらば(他者にも)与えられん……という世の中の、入り口に私たちは生きているのです。
振り返れば、「ワタシの一人」である私には、瀬戸内海のあをさをイメージすることも、3階に行くことの難しさを予想することも、右利きのイラストを見ながら左手で紐通しする困難さを想像することも、できませんでした。
でも、アナタに問いかけ、アナタに教わり、アナタからのリクエストに応えることを通じて、アナタの目線に少しずつ近づくことなら、できているような気がします。
私はこの取り組みを、持続可能な形で皆様と拡げていくために、株式会社こどもめせんを創業しました。
「こどもめせん」は、言葉を一瞬でイラストに変換してくれるAIアプリです。
しかし、それだけではなく、ワタシがアナタの目線を想像しようとする試みであり、ワタシタチをアナタタチと共に創っていこうとする試みなのです。
だから私は、募集します。そのようなシステムのコードを書き、実装のサイクルを加速してくださる、プログラマの方々を募集します。
だから私は、募集します。そのようなシステムの入り口となるアプリを紹介し、共創の輪を広げてくださる、応援者の方々を募集します。
そして私は、募集します。そのようなシステムを活用しながら、育つ方々/育てる方々を募集します。いつかどこかで、ダレカのことをそっとサポートできるのは、アナタの目線――いまお困りの、アナタの目線に他ならないと、私は信じているからです。
ここまで長文をお読みいただき、本当にありがとうございました。メールアドレスは info@children.co.jp です。これから(も)どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
◆ 塙 孝哉 (はなわ たかや)
新潟県立新潟高等学校出身。東京大学医学部医学科卒。小児科専門医。
昼夜逆転・不登校だった弟の一助になればと学部時代に所属した睡眠の研究室で、プログラミングに出会う。以降、東京大学医学部附属病院小児科助教等、小児科医としての臨床業務と、プログラマ・AI研究者としての社会実装活動(IT/AIの強みをいかして医療現場をよりよくする活動)を続け、子どもたちの役に立つ取り組みを加速させるべく、2025年5月に株式会社こどもめせんを創業。本アプリケーションのプログラミングは、今のところ全て自身で行っている。生まれた場所や生まれもった発達特性に関わらず、全ての子どもたちが幸せに生きていける社会の実現が夢。本アプリケーションをその端緒として、応援いただける方々と共に育てていきたいと願っている。
第2回 発達障害があると疲れやすいって本当?:ASDと疲労の関連
───────────────────────────────────…‥・
レデマガ読者の皆様、こんにちは。筑波大学の仲田真理子です。連載「発達障害と疲労」、第1回ではADHD特性と疲労の関係について、とくに不注意特性が強くて、注意のコントロールが難しいヒトは疲労感も強い傾向があることについてご紹介しました。第2回は、自閉スペクトラム症(ASD)と疲労の関連について、生物学的な背景にも触れながらご紹介していきます。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:あまり知られていない発達障害のある人の疲労について 第2回 発達障害があると疲れやすいって本当?:ASDと疲労の関連
───────────────────────────────────…‥・
レデマガ読者の皆様、こんにちは。筑波大学の仲田真理子です。連載「発達障害と疲労」、第1回ではADHD特性と疲労の関係について、とくに不注意特性が強くて、注意のコントロールが難しいヒトは疲労感も強い傾向があることについてご紹介しました。第2回は、自閉スペクトラム症(ASD)と疲労の関連について、生物学的な背景にも触れながらご紹介していきます。
ASDと疲労についての定量的な研究はまだ少ないのですが、英語圏の自閉症当事者コミュニティで生まれた用語であると思われるautistic burnout(自閉症バーンアウト)という現象が最近研究の俎上に上るようになってきました。Raymakerら(2020)の定義を以下に引用します(翻訳は筆者によるもの)。
Autistic burnout is a syndrome conceptualized as resulting from chronic life stress and a mismatch of expectations and abilities without adequate supports.
自閉症バーンアウトは、慢性的な生活ストレスと、適切な支援を受けられない状態での期待される能力と実際の能力に不一致があることから生じる。
It is characterized by pervasive, long-term (typically 3+ months) exhaustion, loss of function, and reduced tolerance to stimulus.
持続的で長期にわたる(通常3ヶ月以上の)疲労感、機能の低下、および刺激に対する耐性の低下が特徴である。
この現象の定量的な尺度を作る試みも行われているようです(Arnold et al., 2023)。
このように、現時点では「自閉症バーンアウト」は疲労そのものではなく、疲労を含む複合的な状況を表す概念ということになっています。ただ、その生物学的メカニズムはおそらく疲労と同じか、かなり近いのではないかと私は考えています。バーンアウトまではいっていないASD当事者の疲労や、ASDとADHDが併存するケースについても、今後の研究が待たれるところです。
限局性学習症(SLD)のある人の疲労については、残念ながらほとんど直接的な研究がなされていないようです。ただしASDやADHDの当事者(高校生以上)も一緒に対象とした調査(高橋ら、2014)では字を書くことで疲れやすいという声が上がっていたり、SLDのある生徒に対する合理的配慮の一環として、休憩を頻繁に取らせるという施策も報告されている(Pingali & Sundararajan, 2017, インドの中学校での調査)ことから、当然SLDと関連した疲れやすさもあると考えられます。
書字については、ASDやADHDのある人を対象とした研究が行われており、ASDのある人は字を書くときに「より多くの身体的努力(physical effort)を必要とする」という報告もあります(Johnson, et al., 2013)。今後は、読み、書き、算数それぞれの苦手さが、どのように疲労感につながるのか研究を広げていくことが必要です。
ちなみに発達障害特性が強いとより疲労感が強い、というところまではある程度明らかになっていますが、これまで調査で得られてきた結果は、あくまでも「発達障害特性」と「疲労感」の2つの測度の「関連」であって、発達障害特性が強い「から」疲労感が強い(因果関係)とは言えないことに注意が必要です。
「それはあくまでも統計学的な話で、結局は発達障害だから疲れるんでしょう?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。もちろん本当のところは、まだ誰も分からない、これから明らかにしていくべきことなのですが、私個人としては「疲労が生じやすいから発達障害特性が強くなる」という可能性についても検討したほうが良いのではないかと考えています。
というのも、発達障害とは関係なく、多くの人が「疲れるとパフォーマンスが変わる」という現象を経験します。例えば人は疲れると作業へのモチベーションが下がり、作業に注意を向け続けることが難しくなったり(Hopstaken et al., 2015)、選択的な注意機能が低下して、周囲の刺激に気を取られやすくなったり、失敗が増えたりします(Faber et al., 2012)。
この、疲れた人が経験するパフォーマンスの変化は、発達障害特性、特にADHDの不注意特性と非常によく似ています。実際に、疲労の程度を調べる「チャルダーの疲労スケール(CFQ)」(Cella & Chalder, 2010, 引用は花輪ら, 2002)による日本語版より)と成人のADHD特性を測る自己報告尺度である「Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-J)」(Kessler et al.,2005, 引用はTakedaによる日本語版より)の質問を比べてみましょう。
例えば「やり始めは問題ないのに続けるうちに気力がなくなっていくことは(CFQ)」と「物事を行なうにあたって、難所は乗り越えたのに、 詰めが甘くて仕上げるのが困難だったことが、どのくらいの頻度でありますか。(ASRS-J)」
「なかなか集中できないことは(CFQ)」と「つまらない、あるいは単調な作業をする際に、 注意を集中し続けることが、困難なことが、どのくらいの頻度でありますか。(ASRS-J)」
そして「記憶力はどうですか(CFQ)」と「約束や、しなければならない用事を忘れたことが、 どのくらいの頻度でありますか。(ASRS-J)」など、似た項目がいくつかあるのがわかります。
では、発達障害のある人の「疲労」は、発達障害のない人の「疲労」とどのように違うのでしょうか?それとも、同じものなのでしょうか?なぜ、発達障害のある人の少なくとも一部は、極端に疲れやすいのでしょうか?生活の改善や、工夫をすれば、疲れやすさは「治る」のでしょうか?現時点で明確な答えはありません。とはいえ、現在行われている発達障害に関する生物学的研究では、その謎に迫りつつあるのでは?と思えるものもあります。
そもそも生物学的にみると、疲労とはどのような現象なのでしょう。私たちの身体は、たくさんの細胞でできています。細胞の中には、ミトコンドリアというエネルギーをつくる工場のような部分があり、ひとつひとつの細胞が酸素や養分を取り込んで、エネルギーを作っています。その過程で、活性酸素という産業廃棄物のようなものができて、どうしても細胞が傷ついてしまいます。
細胞が傷つくと炎症が起こり、細胞は「炎症性サイトカイン」というシグナル分子を細胞の外に放出します。炎症性サイトカインは血流に乗って、脳を含む体中に運ばれます。炎症性サイトカインによって、脳内の疲労を感じるのです。詳しいメカニズムは「疲労とはなにか」(近藤, 2023)という本で紹介されています。
たくさん動いたり、考えたりして細胞を活動させると、多くのエネルギーが必要になり、ミトコンドリア工場はフル稼働します。それによって、細胞も傷つくことが増え、炎症性サイトカインもたくさん出ることになります。疲労感は細胞がたくさん働いて傷ついたから、それを修復するために活動を抑えることが必要だよ、というシグナルなのです。
さて、そのことは発達障害とどのような関係があるのでしょうか。実はASDのある人では、脳や身体のなかで炎症が起こっているのではないか、という結果が多くの研究から得られています。ASDのある人では炎症を促進するはたらきのあるインターロイキン6など複数の炎症性サイトカインの血中濃度が、ASDのない人よりも高いことが報告されています(Zhao et al., 2021)。ADHDでもASDと似たような傾向がみられるようです(Misiak et al., 2022)。これらの現象が、実際に本人の感じている疲労とどのように関連するのかはまだ明らかではありませんし、なぜASDやADHDがあると炎症レベルが高くなるのかもわかっていません。
生まれつき、炎症が起こりやすく炎症を抑えにくい、すなわち疲れやすい体質である、という可能性はもちろんあります。ASDに関連するといわれている100以上の遺伝子のなかには、ミトコンドリアの機能に関連するものも含まれていることから、生活の中で経験するのは同じような負荷であっても、細胞のエネルギーを作る力が弱かったり、傷ついた細胞を修復するのが少しゆっくりだったり、それによって起こった炎症を抑えるのが苦手な体質だったりして、余計に疲れてしまうのかもしれません。
もちろん、認知機能や感覚の特性によって、生活の中で受ける負荷が発達障害のない人よりも大きい、という可能性も大いにあるでしょう。聴覚過敏など、感覚の問題によって疲れるということは、ASDのある人を対象とした調査研究でも、多くの当事者によって語られるところです(Wada et al., 2023)。また、ASDのある人では内受容感覚という自分の体内の状態についての感覚が弱く、自分が今どのような状態かを認識することが苦手な傾向もあります(Itoi et al., 2022)。そうすると疲れたことを感じ取れず、必要なときに休憩ができなくてさらに疲れてしまう可能性も考えられます。
さらに、重要なのはこれらの問題は、決して発達障害のある人個人だけで解決すべきものではないということです。Hullら(2017)の調査では「社会の多数派である定型発達者に合わせる『社会的カモフラージュ』をすると疲れる」ことが提唱されています。発達障害があるといじめなどの被害にあう確率が高いことは良く知られていますが、トラウマがあると炎症が高まることも多くの研究から明らかになっています。したがって、発達障害があることを隠さなくて良い社会、そして発達障害があったとしても幼少期から安全に、安心して暮らせる社会に変わることは、疲労という問題への対処においても非常に重要なことです。
さて、ここまで、発達障害と疲労に関する研究を紹介してきましたが、第三回では少し方向性を変えて、発達障害をオープンにしながらフルタイムで就労している、私自身の生活と疲労のことをお話しようと思います。
引用文献
Arnold, S. R., Higgins, J. M., Weise, J., Desai, A., Pellicano, E., & Trollor, J. N. (2023). Towards the measurement of autistic burnout. Autism, 27(7), 1933-1948.
Cella, M., Chalder, T. (2010). Measuring fatigue in clinical and community settings. Journal of Psychosomatic Research, 69, 17-22.
Faber, L., Maurits, N., & Lorist, M. (2012). Mental Fatigue Affects Visual Selective Attention. PLoS ONE, 7.
花輪治子,中野弘一,筒井未春,簑輪眞澄,土井由利子.(2002). チャルダー疲労質問票日本語版の作成について.第7回慢性疲労症候群(CFS)研究会, 大阪, 第7回慢性疲労症候群(CFS)研究会講演要旨集, p. 38.
Hopstaken, J., Van Der Linden, D., Bakker, A., & Kompier, M. (2015). A multifaceted investigation of the link between mental fatigue and task disengagement. Psychophysiology, 52(3), 305-15.
Hull, L., Petrides, K. V., Allison, C., Smith, P., Baron-Cohen, S., Lai, M. C., & Mandy, W. (2017). “Putting on my best normal”: Social camouflaging in adults with autism spectrum conditions. Journal of autism and developmental disorders, 47(8), 2519-2534.
Itoi, C., Ujiie, Y., Matsushima, K., Takahashi, K., & Ide, M. (2022). Validation of the Japanese version of the Interoception Sensory Questionnaire for individuals with autism spectrum disorder. Scientific Reports, 12(1), 21722.
Johnson, B. P., Papadopoulos, N., Fielding, J., Tonge, B., Phillips, J. G., & Rinehart, N. J. (2013). A quantitative comparison of handwriting in children with high-functioning autism and attention deficit hyperactivity disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 1638-1646.
Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256
近藤一博 (2023). 疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた?. 講談社.
Misiak, B., Wojta-Kempa, M., Samochowiec, J., Schiweck, C., Aichholzer, M., Reif, A., Samochowiec, A., & Sta?czykiewicz, B. (2022). Peripheral blood inflammatory markers in patients with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 118.
Pingali, S., & Sundararajan, J. (2017). A study of reasonable accommodations provided in classrooms to children with specific learning disorders. Journal of Evolution of medical and Dental Sciences, 6, 5195-5199.
Raymaker, D. M., Teo, A. R., Steckler, N. A., Lentz, B., Scharer, M., Delos Santos, A., ... & Nicolaidis, C. (2020). “Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew”: Defining autistic burnout. Autism in adulthood, 2(2), 132-143.
高橋 智,井戸綾香,田部絢子,石川衣紀,内藤千尋(2014).発達障害と「身体の動きにくさ」の困難・ニーズ ― 発達障害の本人調査から ― .東京学芸大学紀要総合教育科学系II.65,23-60
Wada, M., Hayashi, K., Seino, K., Ishii, N., Nawa, T., & Nishimaki, K. (2023). Qualitative and quantitative analysis of self-reported sensory issues in individuals with neurodevelopmental disorders. Frontiers in Psychiatry, 14, 1077542.
Zhao, H., Zhang, H., Liu, S., Luo, W., Jiang, Y., & Gao, J. (2021). Association of peripheral blood levels of cytokines with autism spectrum disorder: a meta-analysis. Frontiers in psychiatry, 12, 670200.
◆仲田真理子(なかた・まりこ)
筑波大学人間系助教。
専門は行動神経内分泌学。ホルモンと社会行動の研究の傍ら、疲労の研究をはじめる。自身が発達障害(自閉スペクトラム症/ASD・注意欠如多動症/ADHD)の当事者であることから、発達障害のある人のための通院・服薬に関する理解促進パンフレット「発達障害の当事者とまわりの人のための薬はじめてガイド」を制作し、無料で配布する活動を続けている。パンフレットは、webサイトよりアクセシブルPDF版をダウンロードできるほか、サイト内の「お申し込みフォーム」より無料で紙の冊子の発送を依頼することができる(病院や学校などには、一度に大量に発送することも可能)。
■□ あとがき ■□--------------------------
10月1日から3日に幕張メッセでメディカルジャパンが開催され、その中の児童発達支援・放課後等デイサービスフェアに出展します。編者の五藤は3日間、1ホール2-45のブースで説明をさせていただきます。入場無料です。お近くの方はぜひお立ち寄りください。
※メディカルジャパン レデックスブース
次回メルマガは、10月10日(金)に刊行します。
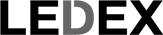

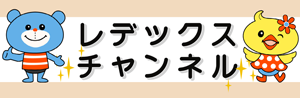
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら