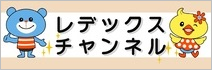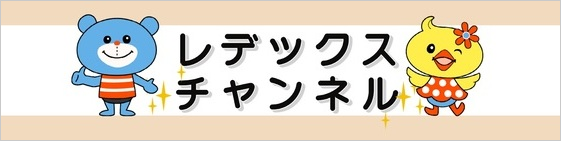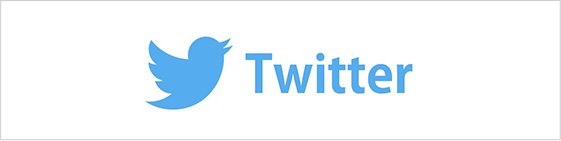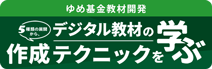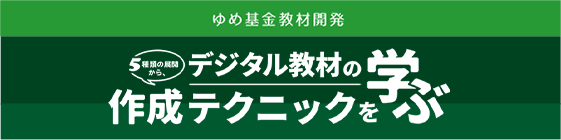----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
今回から連載をしてくださる塙さんをご紹介します。
本メルマガになんどかご寄稿くださっている本田真美先生から、ある研究会で紹介していただきました。その際に見せていただいた試作中のアプリケーションが、とてもスムースにイラストが出てくる様に驚きました。これまで実現したらよいと思っていたことが、AIを用いたシステムの力で可能になるのかもしれません。その応援の意味で、本メルマガに寄稿してもらうことにしました。
塙さんは、東京大学の医学部医学科の出身です。大都市圏の私立校で学び、幼少期から塾通いをしてきたように思われるかもしれませんが、高校卒業まで学習塾とは無縁のまま地方の公立学校で過ごしたそうです。起業家という言葉には、ギラギラとお金を追いかけるイメージが伴いがちですが、塙さんは起業家というより小児科医や研究者という雰囲気がしっくりくる方でした。
第1回 言われたことを一瞬でイラストに変えてくれるアプリ
───────────────────────────────────…‥・
「こらっ! 外来の診察室で立ち歩くなって言ったでしょ!」
■ はじめに
■□ 新連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ
■□■ 連載:まだ光の届かない場所へ、光を届けに行く(最終回)
■□■ 連載:まだ光の届かない場所へ、光を届けに行く(最終回)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
今回から連載をしてくださる塙さんをご紹介します。
本メルマガになんどかご寄稿くださっている本田真美先生から、ある研究会で紹介していただきました。その際に見せていただいた試作中のアプリケーションが、とてもスムースにイラストが出てくる様に驚きました。これまで実現したらよいと思っていたことが、AIを用いたシステムの力で可能になるのかもしれません。その応援の意味で、本メルマガに寄稿してもらうことにしました。
塙さんは、東京大学の医学部医学科の出身です。大都市圏の私立校で学び、幼少期から塾通いをしてきたように思われるかもしれませんが、高校卒業まで学習塾とは無縁のまま地方の公立学校で過ごしたそうです。起業家という言葉には、ギラギラとお金を追いかけるイメージが伴いがちですが、塙さんは起業家というより小児科医や研究者という雰囲気がしっくりくる方でした。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ 第1回 言われたことを一瞬でイラストに変えてくれるアプリ
───────────────────────────────────…‥・
「こらっ! 外来の診察室で立ち歩くなって言ったでしょ!」
診察室に、鋭い声が響きました。両耳をおさえ、ブツブツと独り言を呟きながら歩き回っている男の子を、お母さまが注意されたのです。
男の子は一瞬、顔をしかめて、さっきより強く両耳をおさえながら、いっそう速足で、狭い診察室の中をグルグルと歩き回ります。
「……すみませんねぇ……いつもこうなんです……」
そう気まずそうに苦笑いしながら頭を下げるお母さまの表情には、数年来のお疲れと諦めとが、降り積もっていました。
私は『椅子に座っている子のイラスト』を取り出して、
「椅子に座るよ」
と穏やかに言いました。
※ 椅子に座っている子のイラスト
「……えっ!? ……ぇえっ!?!?」
お母さまが驚いて息をのんだ音が、私の耳にも、はっきり届きました。
「椅子に座れて、偉いね!!」
私は拍手しながら、男の子を褒めます。
「すごい……ね……」
お母さまもつられて、拍手しました。
男の子は、お母さまが自分に拍手してくれるのを見て、得意気に笑い、自分で自分に拍手をすると、そのまま嬉しそうな表情で、きちんと椅子に座っていました……。
小児科の診察室では、こんなことが日常的に起こります。
これは、魔法でしょうか? それとも、発達障害の診断と治療ができる、児童精神科のエキスパートにしか実践不能な、超絶技巧の秘伝でしょうか?
いえいえ、決して、そんなことなど、ありません。
たしかに、読者の皆様がお察しの通り、彼は発達障害です。
医療者の言葉で描写するなら「自閉スペクトラム症・知的障害で、ワーキングメモリが低く、視覚優位」ということになるでしょう。
しかし、もっと簡単に言うなら、彼は
1. 一度にたくさんのことを言われても困ってしまう
2. 耳で聞いた情報より目で見た情報を処理する方が得意な
3. お母さんに褒められたい男の子
だったわけで、私が行ったのも単に
1. シンプルな肯定文で
2. イラストを見せながら指示し
3. できたら褒める
という、基本原則通りの対応にすぎません。
魔法でも秘伝でもなければ、彼が「反抗していた」訳でも、私との「相性が良かった」訳でもなく、単にコミュニケーション方法の問題なのです。
コミュニケーション方法の問題ですから、練習すれば誰でも習得できるはずです。
シンプルな肯定文で、イラストを見せながら指示し、できたら褒めるというサイクルを繰り返すと、次第にお子さんにも自信がつき、できることが増え、子育てが好循環に入りますよ……そんな説明を繰り返しながら、それを実際に行うことの難しさに、頭を抱える日々が続きました。
適切な方法を知っていることと、それを毎日の生活の中で実践できることの間には、大きな3つの壁があったからです。
■ 絵カードを一瞬で選ぶ
第一に「カードを一瞬で選ぶ」ことが、とても大きな壁でした。
診察室で使うカードはせいぜい十数種類ですが、彼の一週間を想像するだけでも、あってほしいカードの数は数百枚をゆうに超えます。
PECSやコバリテ、えこみゅなど、偉大な先輩方の整備してこられた視覚支援グッズは世の中にたくさんあり、コミュニケーションの困難な多くの子どもたちにとって、大きな助けとなっていますが、使いたい絵カードの枚数を増やすと、それを管理して選ぶ側の難易度が、どんどん上がってしまうのです。
チョロチョロと動き回るお子さんから目を離さないよう見守りながら、その子に指示が入る一瞬を逃さず、最適な絵カードを選んで提示する難易度は極めて高く、神業的な記憶力とタスク処理能力、瞬発力と熱意が要求されるため、使える人を選んでしまいます。
特に「音声言語が全く使えない訳じゃないけれど、音にイメージを結びつけるのが他のお子さんより不得手で、周りの様子を伺いながら、おそるおそる行動している境界域のお子さん」は、言葉を全く話されない重症のお子さんに比べて必要な絵カードの量が多いので、親御さんが絵カードを使おうとした場合の難易度がむしろ高くなり、従来の視覚支援グッズでは対応できずに取り残されてしまいがちでした。
※ 境界域のお子さんに役立つサポートの形
■ シンプルに話す
第二に「シンプルに話す」ことが、さらに大きな壁でした。
「こどもたちに理解可能な、必要最低限の単語を選び、複文を避け、目的語と述語を近づけて、余計な修飾語を省きながら話すこと」は、簡単そうに見えて、かなり高度な作業です。
音声言語を何不自由なく、自然に習得された親御さんは「小児科の診察室に入ったら椅子にきちんと座って診察を受けるのが当たり前でしょ?」と言われながら育っておられます。だから自分の子どもにも、同じように言おうとするのは当然です。
そこをグッとこらえて、脳内で「何が一番重要な情報だろう?」と思考を整理し、「椅子に座るよ」という二語文にする……(実は、この整理ができるようになるだけで、絵カードがなくとも、子どもたちとコミュニケーションを劇的にとりやすくなるのですが)これは、よほど言語能力が高く、ご自身の声掛けを客観視できる方でなければ実践できません。
診察室で見かけたときには、言い換えをアドバイスしたりもするのですが、残念ながら医療者の時間は限られており、24時間365日、つきっきりでアドバイスできるわけではありません。親御さんが気づき、理解し、実践できるようになるまで、相当な時間がかかります。
※ シンプルな言い換えの例
■ 否定文を言い換える
最後に、否定文の多用を自覚することが、極めて大きな壁でした。
否定文は、その場で行われていることを禁止するだけなので、話す側にとっては容易です。診察室で立ち歩いている子がいれば「歩かないで」と注意すればいいだけなので、私たちの子育ては、意識しないと否定文だらけになりがちです。診察室で「歩かないで」と言われたら、「普通」は「座る」ものだ、という前提が、「歩かないで」と言う側の脳内には存在します。
ところがこの「歩かないで」という指示、例えば体育の長距離走で、最初から歩いている子に対しても使われるのが厄介です。その場合、「歩かないで」の意味するところは「座れ」ではなく「走れ」ですから、文脈を理解するのが苦手なお子さんたちにとって、かなり難易度の高い解釈が要求されていることになります。
取るべき行動を明示しない否定文は、意味するところが多様なので、取るべき行動を明示される肯定文に比べ、お子さんにとっての難易度が跳ね上がってしまうというわけです。
※ 否定文を解釈することの難しさ
■ こどもめせんのアプリ
24時間365日、親御さんの子育てにつきっきりで伴走し、親御さんにシンプルな肯定文での声掛けを促しながら、数千枚・数万枚の絵カードでも、一瞬で選び出してくれるようなナニカがあればいい……いや、ないと困る子たちが、あまりにも多すぎる……。
そう思った私は、近年進歩が著しい人工知能(AI)の力を借りて、そのようなAIアプリケーションを作ってみました。
お子さんに話しかけるときにボタンを押すだけで、AIが音声を解析し、一瞬で字義通りのイラストを出してくれるアプリです。
誰でも1分かからずに使い方をマスターでき、使っているうちにお子さんへのお声掛けが自然と上手くなります。
※ こどもめせんのアプリ
現在、多くの方々にご協力いただき、現場での調整を繰り返しながら、急ピッチで一般公開に向け推敲を進めているところです。
もし、ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、是非 info@children.co.jp まで、ご連絡いただければ幸いです。
Webサイト
次回以降、「『こどもの視点』に大人が気づくことの大切さ」や「『一方通行の指示・支援』から、『双方向のコミュニケーション・共創』へ」というテーマなど、アプリを通して皆様と目指したい世の中について、もう少し詳しく書かせていただければと思います。(続きます)
◆塙孝哉(はなわたかや)
新潟県立新潟高等学校出身。東京大学医学部医学科卒。小児科専門医。
昼夜逆転・不登校だった弟の一助になればと学部時代に所属した睡眠の研究室で、プログラミングに出会う。以降、東京大学医学部附属病院小児科助教等、小児科医としての臨床業務と、プログラマ・AI研究者としての社会実装活動(IT/AIの強みをいかして医療現場をよりよくする活動)を続け、子どもたちの役に立つ取り組みを加速させるべく、2025年5月に株式会社こどもめせんを創業。本アプリケーションのプログラミングは、今のところ全て自身で行っている。生まれた場所や生まれもった発達特性に関わらず、全ての子どもたちが幸せに生きていける社会の実現が夢。本アプリケーションをその端緒として、応援いただける方々と共に育てていきたいと願っている。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:「“うちの子だけ…?”から始まった、もうひとつの歩み」──母として、そして経営者として── (最終回)
第3回 まだ光の届かない場所へ、光を届けに行く
──仲間とともに育ててきた今、そしてこれから──
───────────────────────────────────…‥・
これまで2回にわたり、なぜ私がこの事業を始めたのか、そして最初の教室をどのように立ち上げたのかをお話ししてきました。
最終回となる今回は、コアヴィレッジの現在地と、これからのビジョンについて綴らせていただきます。
■ 想いだけでは広げられない。でも、想いがなければ続けられない。
最初の教室が開所してから、有難いことにさまざまなご縁をいただきました。
中でも大きな転機となったのが、埼玉県内にある3つの教室との出会いです。
もともとはフランチャイズとして運営されていた施設で、コアヴィレッジとは運営方針や療育内容に違いがありました。
事業譲受のお話をいただいたとき、正直に言えば、迷いもありました。
「やり方が違う中で、私は引き継げるのか?」と。
でも、実際に教室を訪れ、子どもたちの姿にふれたとき、迷いは少しずつ確信に変わっていきました。
──どんなかたちであっても、子どもの可能性を信じて育てたいという“本質”は、きっと同じなんだ。
そう思えたからこそ、私は「やり方を揃える」よりも「視点を揃える」ことを大切にしてきました。
現場のスタッフたちとも何度も対話を重ね、「私たちは、子どものどんな力を信じているのか」「どんな未来を願っているのか」を、言葉にして共有する日々です。
今では、アプローチが違っても、支援の“軸”は一つにつながっていると感じています。
■ 港区に開所した新たなチャレンジ──“感覚統合”を意識した教室づくり
2024年には、東京都港区に多機能型の新しい教室を開所しました。
都市部にある限られたスペースのなかで、どうすれば子どもたちがもっと身体を動かし、感覚を統合する機会をつくれるのか──。その課題に向き合っていたとき、ヒントをくれたのはスタッフの作業療法士でした。
「ボルダリングは、体幹やバランスだけでなく集中力や思考力も育めること」
「サイバーホイールは、楽しみながら平衡感覚を養える優れた道具であること」
そのアドバイスをもとに導入した設備は、今では子どもたちにとって“わくわくするお気に入りの場所”になりました。
※ボルダリング
※サイバーホイール
こうした新たな視点や工夫は、いつもスタッフの専門性から教えてもらっています。
私は、現場を動かす立場であると同時に、現場から日々学ばせてもらう立場でもあるのです。
■ 想いを分かち合う仲間たちと
「子どもたちが、自分の可能性に気づき、育んでいける居場所をつくりたい」
私の中にあったこの想いは、今、同じような想いを抱いてくれる仲間たちと共鳴し合っています。
目の前の支援だけでなく、「この子が大人になったとき、どんな世界が待っているか」までを一緒に想像してくれる人。
子どものほんの小さな変化を、心から一緒に喜べる人。
そうした仲間が、たくさんいます。
だからこそ私は、これからも**「まだ光が届いていない場所」──特に都市部に、もっと教室を届けていきたい**と考えています。
都市部には、情報も選択肢も豊富にあります。
けれどその一方で、子どもたちは幼い頃から受験競争の渦に巻き込まれ、保護者の方々もまた“見栄”や“焦り”といった目に見えないプレッシャーの中で、迷い、苦しんでおられる姿を何度も見てきました。
情報に振り回され、心をすり減らしてしまう親子たち。
そうしたご家庭にこそ、「ここは大丈夫」と思える安心の拠点を届けたい。
そして、教室は“特別な場所”ではなく、“日常に自然に溶け込む場所”でありたいのです。
普段過ごしているお洒落な街並みにもなじみ、ふと立ち寄れるような。
そんな“通いやすさ”や“入りやすさ”も、私が大切にしていきたい価値のひとつです。
■ そして今、次の“種”を構想しています
実は今、私は新たなチャレンジをしたいと考えています。
それは、“教育”と“療育”がやわらかく融合した、新しい支援のかたち。
まだ詳細はお話できませんが、
これまでずっと私の中で育ててきた“あたらしい選択肢”の構想です。
療育と教育がもっと自由に交わり、
「こんな場所、なかったよね」が「ここにあってよかった」に変わるような場所を、つくっていきたい。
その種が、確かな芽となって育つよう、これからも努力を続けてまいります。
■ 最後に──“あの日”の私に届くように
私は、何か特別な資格を持っていたわけでも、特別な環境があったわけでもありません。
ただ、「グレーゾーンの子でもどんな子でも生きやすい社会であってほしい」と願った、ひとりの母でした。
でも、少しずつ、一歩ずつ、想いに仲間が集まり、場所が増え、できることが広がってきました。
このメルマガを読んでくださっている方の中にも、今まさに悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません。
どうか、あなたの中にある小さな違和感や、小さな願いを、大切にしてください。
その想いが、いつか誰かの希望になる日が、きっと来ます。
私たちはこれからも、その“光”を届ける仕事をしていきます。
◆山田広恵
TV局で報道やイベント企画・運営に携わった後、結婚を機にブライダル業界へ転身。全国展開企業のエリアマネージャーや独立後の経営を経て、2024年3月にブライダル事業を譲渡。現在は、東京都内に3教室、さいたま市内に2教室を展開する児童発達支援事業の経営・運営に専念している。直営の教室である「コアヴィレッジ」では、子どもの得意・不得意を科学的に分析し、苦手の克服や自立支援だけでなく、“当たり前”の一歩先を目指した支援を提供している。
■□ あとがき ■□--------------------------
次回メルマガは、9月12日(金)にお届けします。
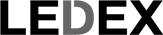

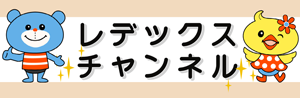
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら