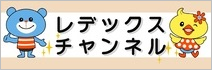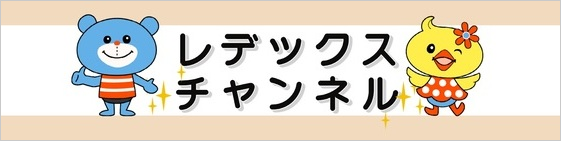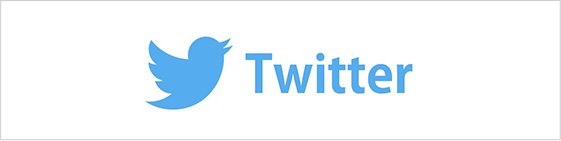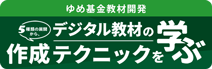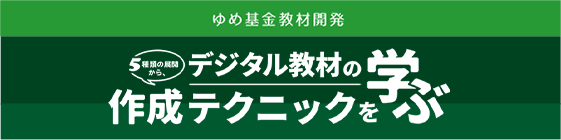----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■ まえがき
■□ 新連載:「AIセラピストco-mii」がつくる発達支援の未来
■□■ 連載:読み書き集団アセスメント
■□■ 連載:読み書き集団アセスメント
--------------------------------------------------------------------------------------------------
■□ まえがき ■□--------------------------
AIを使って個別支援を行うという試みに挑戦している株式会社ヴィリング代表の中村一彰さんに、今回から3回の連載で、同社の取り組みについて紹介していただきます。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:「AIセラピストco-mii」がつくる発達支援の未来第1回 発達支援の第一歩!アセスメントの基本とNG例
───────────────────────────────────…‥・
1.発達支援の現場で求められる視点
施設内に響く職員の声。部屋を飛び出そうとする子どもを必死に止める職員。しかし、子どもはイライラしていて、なかなか落ち着かない。
放課後等デイサービスや児童発達支援事業所では、こうした場面に遭遇することが珍しくありません。特に支援経験の浅い職員にとって、対応に困ることも多いでしょう。
発達支援の現場における主な課題は、次の3つです。
1)子ども一人ひとりに合わせた支援の難しさ
発達障害のある子どもは、それぞれ異なる特性を持っています。自閉症スペクトラム、ADHD、知的障害など、多様な支援ニーズに応じた対応が求められますが、適切な関わり方を見極めるのは容易ではありません。
2)保護者との連携の難しさ
保護者とのコミュニケーションは支援の成功に不可欠です。しかし、経験が浅いと「どのように説明すれば理解してもらえるのか」「どこまで支援方針を共有すべきか」と悩むこともあります。
3)精神的な負担の大きさ
子どもの感情の爆発やパニック対応が続くと、職員の精神的な負担も大きくなります。
こうした課題を解決するカギとなるのが、「アセスメント」です。
2.アセスメントとは?
では、アキラくんのような子どもに対して、どうすれば効果的な支援を提供できるのでしょうか?
職員の皆さまには、まず理解しておいていただきたいことがあります。
それは、アキラくんのような子どもは、言葉での理解や表出ができるために、こちらが伝えていることを全て理解しているように見えますが、実はそうではない場合があるということです。
また、発達障害を抱える子どもたちの行動のほとんどは、障害の特性から起因していることです。
そのため、決してわがままではないということを理解して頂きたいです。
この部分を理解するためにも重要なのが「アセスメント」です。アセスメントとは、子どもの行動や特性を評価し、適切な支援方法を見つけ出すプロセスです。アセスメントを活用することで、子どもの行動の原因を特定し、効果的な支援を提供することで、子どもたちとの信頼関係を深めることができます。
具体的なアセスメント方法として、アキラくんが部屋を飛び出す前にどんな状況があったのか、支援中にどの程度集中できていたのか、他の子どもとの関係性に問題があったのかなど、行動の背景を探ります。
例えば、アキラくんのように「部屋を飛び出す」行動の背景を探るためには、以下の点を確認することが考えられます。
・椅子を後ろに傾けたり、揺らしたりして座るのか
・学習課題が終わるまで集中することができるのか
・周囲の状況に左右されることなく集中力を保てるのか
・好きなことをしている時に次の行動に移れない
・気持ちの切り替えに時間がかかる
・忘れ物が多い
・順番を待つことが苦手
・自分の思い通りにならないと怒ることがある
・我慢することが苦手
・暴言や蹴る、叩くなどの行動が多い
・思いつくことをすぐ口にだしてしまう
などを確認します。
これらの確認は、ADHDの特性である衝動性や多動性、不注意さが行動にどれほど影響を与えているのかを理解するための手がかりとなります。
衝動性が強く、予測できない行動をとる子どもに対しては、支援中の注意を引くための視覚的な手がかりや、落ち着くためのスペースを提供することが効果的です。
また、支援中に短い休憩を取り入れることも、集中力を維持しやすくする工夫の1つとして考えられます。
アセスメントを基にした具体的な支援方法を導き出すことで、子どもの行動を良い方向につなげ、職員の精神的負担を軽減することができます。
3.アセスメントと行動観察の違い
次に、アセスメントと行動観察の違いについて考えてみましょう。アセスメントと行動観察は似たように思えるかもしれませんが、実際には異なるプロセスです。
行動観察では、子どもがどのような行動をしているのかをそのまま捉え、見守ることが中心となります。たとえば、授業中に子どもがどのように動いているか、どんなふうに反応しているかを観察し、その場で起きていることをしっかりと理解しようとします。
一方で、アセスメントは、その観察を基に、なぜその行動が起きているのか、その背後にどのような理由や背景があるのかを探り、理解するためのプロセスです。
単に「こういう行動があった」という事実に留まらず、「どうしてその行動が起こったのか」を深掘りして考えることがアセスメントには求められます。
病院を例に考えてみましょう。たとえば、腹痛で病院を受診したとします。精密な検査をせず、簡単な問診だけで鎮痛剤を処方されたら、どう感じるでしょうか?
腹痛の原因は、胃や腸、肝臓などさまざまな可能性があります。しかし、根本的な原因を調べずに、痛みを和らげるための鎮痛剤だけを処方し続ける??こうした対症療法が、発達支援の現場でも実際に行われているのです。
たとえば、「字が上手に書けないから、ひたすら書く練習をさせる」という対応も、対症療法の一例です。
では、適切なアセスメントを実施すると、どのような支援が可能になるのでしょうか?
例えば、支援中にある子どもが何度も集中を切らして手遊びをしている場面を考えてみましょう。
行動観察の段階では、「支援中に手遊びをしている」という事実を捉えるだけで終わりますが、アセスメントでは、なぜその子どもが手遊びをしてしまうのか、その理由を探ることに焦点を当てます。
この場合、アセスメントを通じて、子どもが周囲の刺激に対して過敏であることや、部屋の環境が集中力を妨げている可能性を考えることができます。また、その子どもにとって、もっと興味を引く教材が必要なのではないかという視点も浮かび上がるかもしれません。
こうした情報に基づいて、「手遊びをやめさせるように注意する」こともできますが、それだけでは問題が根本的に解決されるとは限りません。
どうすればその子どもがもっと集中できる環境を提供できるのか、どんな支援が最適なのかを考えることが重要です。
※ここで行われている全体のプロセス=「アセスメント」

アセスメントを行うことで、その子どもがなぜ特定の行動を取るのかを理解し、その子に合った対応策を考えることができるようになります。
その結果、問題の根本的な解決を目指し、より効果的な支援が可能になります。4.根本的な解決を目指して
一時的な解決策やその場しのぎの対応ばかりしてしまうと、子どもが同じ行動を何度も繰り返してしまう可能性があります。
例えば、叱ったり、注意を繰り返したりするだけでは、子ども自身が自分の行動の理由を理解することができず、結果として同じ問題行動を続けてしまいます。これにより、子どもは自分が「また失敗した」「また怒られた」と感じ、自分自身に対する評価が下がり、自己肯定感が低下してしまう恐れがあります。
自己肯定感が低下すると、子どもはますます「どうせ自分はできない」「誰も自分のことを理解してくれない」といったネガティブな思考に陥りがちになります。
さらに、先生からの注意や指導が続くと、子どもは次第に先生に対して反抗的な態度を取るようになることもあります。
このような状況が続くと、子どもと先生の信頼関係が損なわれ、学びの場がストレスの多い場所となってしまい、最悪の場合、二次障害につながる恐れもあります。
二次障害とは、元々の問題に加えて、新たな精神的・感情的な問題が生じることを指します。例えば、過度なストレスや自己肯定感の低下が引き金となり、不安やうつ状態が進行する場合があります。このような状態になると、子どもの学習意欲や生活全般に大きな影響が出てしまうため、早めの対策が重要です。
こうした悪循環を避けるためには、アセスメントを通じて子どもの特性や行動の背景をしっかりと理解し、その子に合った支援や指導を行うことが重要です。
アキラくんのエピソードを振り返ってみても、適切なアセスメントがあれば、彼の衝動性や多動性の背景にある要因を理解し、それに合ったサポートを提供することで、彼の行動を改善する道が開けたはずです。
※根本的な解決を目指して子どもが二次障害に陥ってしまうサイクル図 https://bit.ly/4hIDEy0
二次障害を防ぐためには、アセスメントを活用し、子どもの特性や行動の背景をしっかりと理解した上で適切な支援を行うことが重要です。
5.アセスメントを活用し、より良い支援を
支援の現場では、アセスメントを活用することで、より適切な関わり方ができるようになります。
また、自治体と連携し、アセスメントに関する研修を開催したり、デジタルツールを活用した支援システムの提供も行っています。
支援者自身が自信を持って子どもと向き合うことで、より良い支援につながります。
ぜひ、日々の支援にアセスメントを取り入れてみてください。
次回のメルマガでは、「報酬改定の影響とAIセラピストco-mii」 をテーマにお届けします。
支援現場に影響を与える報酬改定のポイントと、それに対応するためのAIセラピストco-miiの活用方法について詳しく解説します。
現場の負担を軽減し、より効果的な支援につなげるためのヒントをお届けしますので、ぜひご覧ください!
◆中村 一彰
株式会社ヴィリング 代表取締役
STEAM教育スクール「STEMON(ステモン)」、放課後等サービス向け療育教材「すてむぼっくす」、発達障害AIアセスメント「co-mii」、バイリンガル英語家庭教師「お迎えシスター」などを運営。著書『AI時代に輝く子ども』『放課後等デイサービス 5領域に対応療育トレーニング50』
所属学会:日本LD学会、日本授業UD学会
◆小嶺 一寿
AIセラピストco-mii 開発者
株式会社みやとの作業療法士。療育センターや福祉の児童分野で16年以上の経験。著書『放課後等デイサービス 5領域に対応療育トレーニング50』
※AIセラピストco-miiとは
AIセラピストco-miiは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス向けの支援システムです。
5領域に対応した「アセスメント」の実施
「個別支援計画書」の半自動作成
アセスメント結果に基づいた「療育メニューの提案」
「専門的支援計画書」の半自動作成
これにより、支援の質を向上させるとともに、業務の効率化にも貢献します。
詳しくはコチラ
お問い合わせ先:TEL:03-5303-9850 MAIL:sales@viling.co.jp
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:読み書きのアセスメントをして子どもの本来の力を発揮する第3回 読み書き集団アセスメント
───────────────────────────────────…‥・
読み書きのアセスメントやスクリーニンができる機関が少しずつ増えてきていますが、人口の8%いる人たちへ行きわたるのはまだまだ先の話になりそうです。そこでNPO法人エッジでは3年前から集団アセスメントを試みています。これまで東京都港区全域の希望者、広島県呉市の小学校と小田原市の小学校の一学年で実施できたので、シェアしたいと思います。
まず東京都港区では集団アセスメントを開始する前に、2021年と2022年に東京都の助成金ですべての児童生徒にチラシを配布し、保護者向けの説明会を開催しました。チラシには表面は保護者向けのメッセージ、裏には子ども向けのメッセージを入れました。実際に手にした児童が、保護者に自分はこれだから連れて行ってと頼んで家族で説明会に来てくれ、その後個別の相談・アセスメントにつながりました。
2023年と2024年は日本財団の助成金で集団アセスメントを実施しました。教育委員会の協力を得て、チラシを11000人の児童生徒全員に配布し、希望者に集団でアセスメントを受けてもらいました。200名程度の希望者にアセスメントをして結果を一人一人に渡すことができました。
事前に希望者向けの説明会を開催しました。アセスメントは10人程度の集団で実施しました。結果はA4一枚に読み書きの困難さの程度が流暢性と正確性について記述され、音声で聞いたほうが分かり易いのかが色分けされています。困難な領域と程度に対して対処できることのリストが記述されています。保護者に渡す目的だったので学校とよく相談して対応を進めるように勧めています。事後にも説明会を開き、結果の読み取り方や家庭学習の方法や学校との連携の仕方について説明しました。
広島県呉市の場合は学校が主体となって教員の方たちがアセスメントをして集計や分析はエッジがしました。教員向けの研修を初めに行い、その上でのアセスメントでした。小田原市の場合は有志の教員たちが数か月にわたって勉強会を開催して準備をして、ある学校の一学年に対して実施しました。こちらも教員がアセスメントをして、エッジで集計と分析をして、その結果を学校と教員にお知らせしました。どちらも思っていたよりも多くの児童生徒が困難さを見せたことが分かり、インクルーシブな授業作りにより一層取り組むことができるようになりました。
港区で集団アセスメントを行った後のことを少しお話ししましょう。
Aさん:小学校3年生で頭は悪くないはずなのに国語がなぜか苦手で、特に漢字を覚えられないし、作文を書くと分量が少ないです。算数も計算は得意なのに文章問題になると分からないのはなぜだろうと不思議に思っていた時にチラシを見ました。不登校気味でもあったので早速申し込んでアセスメントを受けたところ、読み書きの流暢性も正確性も低く出て、音で聞いた方が分かり易いことが分かりました。
家庭で音声教材BEAMを聞いたところ、内容理解ができて授業に参加ができるようになりました。担任に結果を見せたところ、学校でもできることから始めるということで、タブレットを活用して板書は写真に写してそれを後でノートに貼る、漢字テストは選べる形にする、記述式の答えはひらがなでも良しとし、音読の宿題はBEAMを聞くといった負担にならない変更と調整を開始しました。
Bさんは小学校5年生で活発なスポーツ大好きな男の子です。保護者はスポーツばっかりやっていて、勉強しないから漢字を覚えないのだと思っていて、夜中まで宿題をさせていました。疲れやすく少し反抗的な態度をとることも出てきていました。Bさん自身がチラシを見て、お母さんに「これは僕のことだから連れて行って!」と頼んだのです。驚いた保護者が説明会に親子で参加して初めて我が子の困難さを理解することができました。
アセスメントの結果はそこまで顕著ではないものの読み書きの正確性に困難さが見られました。その結果を親子で見て、子どもから具体的にどこか大変だという話を聞くことができて、保護者も対応を改めて、学校とも相談して、宿題の量を調整する、学習の仕方を本や教科書の文字からだけ学ぶのではなく、動画や体験など五感を使った本人に合った方法に変更するなどしたところ、夜寝る時間を確保できました。試験の際に選択問題にするとか、初めは口頭で聞くと正解ができるので、興味を持っている社会でも試験で点数を取ることができるようになり、親子関係も改善しました。
「よく、怠けているだけではないのか?」「頑張って書かせなければ書けなくなってしまうのではないか?」などといわれなかなか対応を始めてくれない現場を見かけます。そしてそのように思い込んでいる保護者もいます。
アセスメントをすることで、対応をする根拠となる数値を出すことができます。様子を見るとかして、すっかりと手遅れにならないようにしてほしいです。
〇その他の資料
【読み書きの集団アセスメント発表会】2024年2月24日に開催しました
読み書き困難指導・支援講座「子どもの味方の教え方」(e-ラーニング)
読み書きアセッサー養成講座(e-ラーニング)
音声教材BEAM:文部科学省委託事業 無償提供
◆藤堂栄子(Eiko Todo)
認定NPO法人エッジ 会長
(NPO EDGE Japan Dyslexia Society)
NPO法人エッジエッジは読み書きの困難を持つディスレクシアの人たちが本来の力を発揮し活き活きと暮らせる社会を目指して活動をして21年になります。これまでの活動は皆様のご支援、お力添えによって実施、継続をすることができました。今後も活動をより多くの方に届けられますように、皆様のご寄付をお願いいたします。■□ あとがき ■□--------------------------
当メルマガの発行元、レデックス株式会社の本社が移転します。新本社の営業開始は、3月31日です。
※新住所 194-0001 東京都町田市つくし野1-31-3 2F
レデックスが提供している放デイ・児発向けアセスメントツール「脳バランサーキッズ」が進化し、「脳バランサ―キッズ2(ツー)」というクラウド版の新サービスとして4月8日にスタートします。
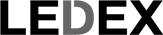

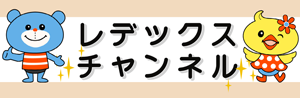
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら