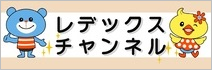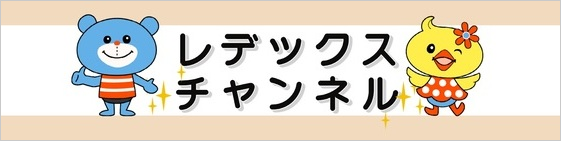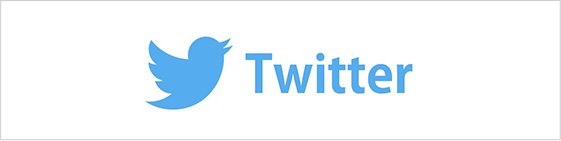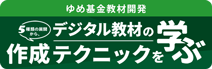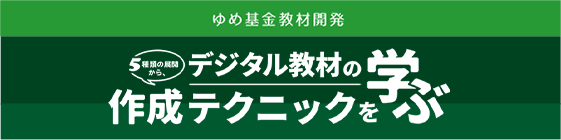----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■ まえがき
■□ 連載:これからのICTはどうなっていくのか(未来):最終回
■□■ コラム:本や映画の当事者たち(13) 映画『美晴に傘を』
■□■ コラム:本や映画の当事者たち(13) 映画『美晴に傘を』
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2025年が始まりました。当メルマガは、2010年の創刊から15年目になります。
本年も読者の皆さま、どうか引き続きご愛読をお願いいたします。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:福祉・特別支援教育におけるICT機器~過去から未来へのICT機器の活用を考えてみよう~
第5回 これからのICTはどうなっていくのか(未来):最終回
───────────────────────────────────…‥・
福祉や特別支援教育の分野におけるICTを活用した支援は、今後さらに進化しさまざまな形で効果的な支援が提供されることが期待されています。
1 パーソナライズされた支援
AIや機械学習を活用した個別化された教育プログラムや支援ツールが発展することで、個々のニーズに応じた柔軟な支援が可能になります。特に自閉症や学習障害を持つ児童生徒に対し、進捗や得意分野、苦手分野をリアルタイムで把握し、それに基づいた学習プランを自動で提供するシステムが広まる可能性があります。
2 コミュニケーション支援の高度化
発話が難しい人やコミュニケーションに障害を持つ人向けの支援として、音声認識やテキスト読み上げ機能、ジェスチャー認識などの技術がさらに発展し、スムーズな意思疎通をサポートするツールが普及していくでしょう。視覚や聴覚に障害がある人のための支援デバイスも、より直感的で使いやすくなると考えられます。
ALSの患者さんや故人の生きていた頃の音声からAIを活用して合成音声を作成することも更に精度が高くなることと思います。
お母さんが不在のときでも、音声読上げ機能がお母さんの声で本を読み聞かせてくれるような時代がくると楽しいですよね。
(参考)話せなくなるALS患者の"自分の声"を救う。「ALS SAVE VOICE」プロジェクトがスタート。
(参考)Alexaが亡くなった人の声を1分未満の音声から学習して模倣できるようになる
(参考)UCLAが手話を翻訳して音声変換する手袋を発表!
(参考)考えるだけで通信できる技術 ブレイン・コンピューター・インタフェース
3 バイオプリンティングの可能性
3Dプリンターを使った臓器作成、いわゆる「バイオプリンティング」の技術は、今後の医療や福祉分野に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。
既に実験レベルで、皮膚や軟骨、血管など比較的単純な構造の組織を3Dプリンターで作成することが成功しています。これにより、外科手術後の再生医療や、火傷患者への皮膚移植に使用される可能性があります。
(1)臓器移植待機者の減少
臓器提供者が不足している現状に対し、3Dプリンターで作られた臓器が移植用として使えるようになれば、臓器移植待機リストの短縮につながる可能性があります。
(2)創薬や医療研究の進展
実際の人間の臓器に近い3Dプリンティングで作成された組織や臓器を使うことで、新薬のテストや治療法の研究が飛躍的に進むと考えられます。これにより、動物実験の代替としても期待されています。
(3)再生医療への応用
患者自身の細胞を用いて作られた組織や臓器は、拒絶反応のリスクが低いため、再生医療の分野で大きな可能性があります。事故や病気で失われた臓器や組織を再生する技術として活用されるでしょう。
(4)福祉分野での応用
障害を持つ児童や患者向けに、個別に調整された補装具や義肢を迅速に作成できる技術が進化しています。さらには、視覚や触覚で学ぶための3D教材の作成も、教育の現場で役立つでしょう。
(資料)かんたん解説「バイオプリンティング」
4 モビリティと自立支援の向上
(参考)口パクの顎の動きで音声認識 イヤフォンに後付け可能
5 リモート学習・支援の普及
特別支援教育の分野でも、リモート学習の導入が進むと予想されます。特に遠隔地に住む児童生徒や、通学が難しい場合でも、ICTを活用することで質の高い教育や支援を受けることが可能となります。また、センサーやバーチャルリアリティ(VR)を使って、リハビリや社会参加のトレーニングを行う環境が提供される可能性もあります。
教員や福祉関係者のなり手不足にもメタバースや遠隔医療の技術は大きな可能性を感じます。
(参考)"メタバース学習塾"が生徒を刺激? アバターが高める積極性
(参考)遠隔医療に関するホームページ
6 AR・VRに次ぐ技術IR
IRとは"接続現実"ともいわれる新しいテクノロジーで、チームラボ※が開発・特許を取得しています。この技術は、人々を取り囲む現実空間と個人が持つデジタルデバイスが相互に影響を与え合うというもので、従来のARと似ているようで全く異なっています。
※チームラボ
スマホなどのデジタルデバイスを使用して、普段私たちが目にする現実空間に変化を起こし、また逆に現実空間での変化がデジタルデバイスに影響を与えるというものです。従来のARがディスプレイを通して見た現実世界のみが変化するのに対し、IRは実際に肉眼で見ている目の前の現実世界が、デバイスを使った人々の行為によって影響を与え合い、変化し続けます。
(資料)スマホと現実空間が互いに影響を与える新技術「IR」が登場!
7 データ活用による支援の最適化
児童生徒の学習や行動データを収集し、分析することで、個々の進捗状況や支援の効果を把握し、教育や福祉の現場での支援をより効果的に設計できるようになります。これにより、支援の質が向上し、教師や支援者の負担も軽減されるでしょう。
ICT分野の進歩は「ドックイヤー」とも言われ凄い速度で進化していきます。
・パソコン・インターネットが普及したのは20~30年
・スマートフォンが普及したのはわずか10年ぐらい
どちらも今では当たり前の機器となり、手紙や固定電話・公衆電話よりもはるかに利便性が高く無くてはならない機器となっています。
今回ご紹介した将来のICT機器の活用がどこまで実現するかは分かりませんが、益々加速していく少子高齢化などを考えると福祉・特別支援教育の分野での支援者不足は必ずやってきます。
人間とICTとの役割(出来ることと出来ないこと)を明確にしていきながら共に進化していきたいですよね!
◆高松 崇
NPO法人支援機器普及促進協会 理事長
関西大卒。ICT・福祉情報機器コーディネーター。民間企業のシステムエンジニアなどを経て43歳で独立。2011年、障害児・者の学習や生活支援用の機器を提供するNPO法人「支援機器普及促進協会」を長岡京市に開設した。
現在は京都市教委総合育成支援課専門主事なども務める。長岡京市在住。
───────────────────────────────────…‥・
■ コラム:本や映画の当事者たち(13) 映画『美晴に傘を』
息子や夫、父を失った家族の再生と自閉症の娘の成長を描く物語
───────────────────────────────────…‥・
タイトルからもわかるように、いわゆる障害や病気などの当事者といわれる人たちが描かれている本や映画、DVDなどを紹介します。
今回は映画『美晴に傘を』です。この映画は2025年1月24日より東京・YEBISU GARDEN CINEMAほかで公開されます。北海道余市での心に傷を負った家族の日常を描きながら、それぞれの人間の成長を描いた良作です。
息子や夫、父を失った家族の再生と自閉症の娘の成長を描く物語
北海道の余市を舞台に、初老の父とがんで亡くなった息子の家族がきずなを結んでいくまでの物語です。
漁師である善次には喧嘩別れした一人息子(光雄)がいました。その息子ががんで亡くなり、息子の妻透子が2人の娘を連れて法要に訪れます。初めて会う嫁や孫娘に戸惑う善次と、透子と娘たちがぶつかりながらも寄り添うように生きる姿が淡々と描かれます。
升毅(ますたけし)が頑固な祖父善次(光雄の父)を、田中美里が美晴の母透子を演じ、そのほかのキャストも芸達者ぞろいで自然な演技でそれぞれの思いが伝わってきます。
不器用な善次は、息子への愛情を胸に秘めながらもそれを伝えることができず、亡くなるまで手紙の返事を出すこともありませんでした。それは、嫁である透子とその娘達にも同様で、気持ちをうまく伝えることができず、ギクシャクしてしまいます。
長女美晴(日高麻鈴)は聴覚過敏の強い自閉症で、20歳になるのですが、しっかり者の妹や母親透子に守られ、生きてきました。まるで、亡き父光雄が美晴のために書いた絵本、『美晴に傘を』の世界のように……。美晴は周囲の大きな音やガヤガヤとした騒音、初めての場所が苦手で怖いことがあると布団をかぶって絵本の世界にこもります。
最初は上手くいかなく見えたその家族が、余市の町の人たちに見守られ、少しずつですが成長します。殻を破り一人の女性として父が美晴を守るために用意した傘を捨てて生きていこうとします。
娘を守ることが、エゴであり、美晴の成長を阻んでいると気付く透子も、善次や町の人の善意で、美晴を守るためのこだわりから解放されます。
息子を愛しながらも拒絶していたことを後悔する善次。愛する人に愛を伝えようとする美晴。さまざまな人の気持ちが交差し、糸から布を紡ぐように家族のきずなが紡がれます。妹である凛を通じて、きょうだいの問題も描かれます。
この映画には悪い人は一人も出てきません。素朴な町とそこに住む人たちの温かい空気感に包まれた世界の中で、見ているととても幸せを感じられます。こんな町なら私も住んでみたい、こんな家族がいたらいいなと思え、日々の暮らしを大切にして生きていくことが幸せだと感じられる映画です。
上映情報
キャスト:升 毅、田中美里、日高麻鈴ほか
脚本・監督 渋谷 悠
制作プロダクション アイスクライム キアロスクーロ撮影事務所
配給 ギグリーボックス
(c)2025 牧羊犬/キアロスクーロ撮影事務所/アイスクライム
◆はら さちこ
ライター。
編集制作会社にて、書籍や雑誌の制作に携わり、以降フリーランスの編集・ライターとして活動。障害全般、教育福祉分野にかかわる執筆や編集を行う。障害にかかわる本の書評や映画評なども書いている。
主な編著書に、『ADHD、アスペルガー症候群、LDかな?と思ったら…』、『ADHD・アスペ系ママ へんちゃんのポジティブライフ』、『専門キャリアカウンセラーが教える これからの発達障害者「雇用」』、『自閉症スペクトラムの子を育てる家族を理解する 母親・父親・きょうだいの声からわかること』『発達障害のおはなしシリーズ』、『10代からのSDGs-いま、わたしたちにできること』などがある。
■□ あとがき ■□--------------------------
次回は1月24日(金)にお届けします。
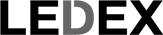

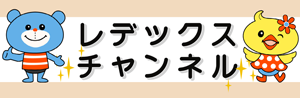
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら