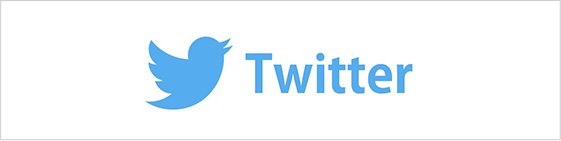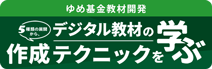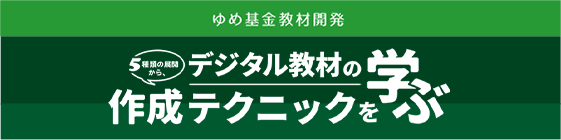----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:発達障害などの子どもが将来希望の就職を実現するための就職塾
第2回 ペガサス就職塾での将来の仕事を意識した活動
───────────────────────────────────…‥・
今回は、社会性やコミュニケーションなどに苦手さのあるお子さんが早くから将来の就職に向けて準備するための、就職塾の取り組みについての2回目です。就労支援事業所ペガサス代表の木村さんと、教育現場で教員一筋にがんばってきた高梨さんとの2人の思いが通じ合い、実現したものです。
■ 連載:ペガサス就職塾での将来の仕事を意識した活動
■□ 連載:「医教連携」による教員養成科目の開講まで---------------------------------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:発達障害などの子どもが将来希望の就職を実現するための就職塾
第2回 ペガサス就職塾での将来の仕事を意識した活動
───────────────────────────────────…‥・
今回は、社会性やコミュニケーションなどに苦手さのあるお子さんが早くから将来の就職に向けて準備するための、就職塾の取り組みについての2回目です。就労支援事業所ペガサス代表の木村さんと、教育現場で教員一筋にがんばってきた高梨さんとの2人の思いが通じ合い、実現したものです。
今回では、ペガサス就職塾の活動について具体的にお伝えします。
就職塾で行う活動内容についての概要は前回お伝えしました。
今回は、回覧板のセッティングとポスティングについてまずお伝えします。
就職塾がある平塚市のある地域では自治会長が回覧板を配っていましたが、担い手がいなくなり困っているという話を聞き、地域のためにも子どもたちの将来のためにもなると思い、回覧板を回したり、掲示板に貼ったりする作業を、子どもたちが手伝うことにしたそうです。
回覧してもらうチラシなどの用紙をまとめ、各家庭数をセットしてホチキスで留め、ポスティングする作業が主になります。委託契約をし、作業代金をいただき、子どもたちも報酬を得られるようにしました。
ある時、「ホチキスの止める箇所によって、その内容が読みにくくなり、見にくい」というクレームが入ったことがあったそうです。
それは作業を見直す良い機会になりました。クレームについて皆で話し合い、対応方法を考え、実行に移すことで、ステップアップしていきました。
この取り組みは、第二回平塚市みんなのまちづくり事例年間大賞をいただきました。
子どもたちは作業の報酬をいただき、そのお金をコンビニなどでの買い物学習に役立てています。買い物をせずに貯めている子もいます。仕事をして報酬をもらうということで、将来の仕事をイメージすることができます。
作業の後には各自振り返りを行います。
回覧板業務の生徒の感想を紹介します。
●仕事をすることで、頭を使い計画的に配布することに気づきました。僕は、自然に声掛けやサポートができるように成長できたと思っています。給料は、自分で働き有効的に考え、大切に使える環境に感謝しています。M
●回覧板を丁寧にプリントを整え袋詰めすることが出来ました。地域貢献している実感できて良かったです。自分で稼いだお金でアイスが買えました。S
●ホチキス止めの場所がわかるようになりました。チラシをそろえることが大事だとわかりました。紙をそろえるのが速くなりました。もらったお金で買ったアイスクリームが美味しかった。K
●僕は回覧板のセッティングの確認が大事だとわかり、紙を目で数えるようになりました。給料でTOICA※を買いました。自分のお金で買って、嬉しかったです。 T
※編者注 TOICA JR東海の交通系ICカード
ほかにも、ある企業から受託した商品の梱包作業も行っています。商品を袋に入れてシールを貼る仕事ですが、やっていくうちにスピードが上がるし、きれいに梱包できるようになっています。発達に難しいところのある子どもたちは、不器用な子が多いけれど、商品がよく見えるようになど、子どもなりに工夫しているところも見られています。
次回は、子どもたちの成長についてくわしくお伝えします。
フリー編集者・ライター
障害福祉や教育関係の書籍や雑誌、進学情報誌等の編集や取材・ライティングを行う。また、執筆だけでなく、コミュニケーションや発達障害についてセミナーやワークショップ講師としても活動中。 全国手をつなぐ育成会機関誌『手をつなぐ』では、映画や本、舞台の評を不定期に連載中。
主な編著書に、
『ADHD、アスペルガー症候群、LDかな?と思ったら…』、『ADHD・アスペ系ママ へんちゃんのポジティブライフ』、『専門キャリアカウンセラーが教える これからの発達障害者「雇用」』、『自閉症スペクトラムの子を育てる家族を理解する 母親・父親・きょうだいの声からわかること』などがある。
2021年3月、平凡社より「発達障害のおはなしシリーズ3巻」、大月書店より「10代からのSDGs-いま、わたしたちにできること」上梓
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:発達障害を支える教員の養成
第2回:「医教連携」による教員養成科目の開講まで
───────────────────────────────────…‥・
さて、前回は長崎大学で、発達障害を学ぶ科目を、どうして「医教連携」をコンセプトに据えたか、という前置きを長くお話しさせていただきました。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:発達障害を支える教員の養成
第2回:「医教連携」による教員養成科目の開講まで
───────────────────────────────────…‥・
さて、前回は長崎大学で、発達障害を学ぶ科目を、どうして「医教連携」をコンセプトに据えたか、という前置きを長くお話しさせていただきました。
今回は「医教連携」による教員養成課程必修科目の開講に至るまでのお話をしたいのですが、その前に、科目の開講に至る、私自身の話をさせてください。
またもや前置きかもしれませんが、私が、ずっと「医」と「教」をさまよったこと、そのはざまにあって、これをつながない限り子どもたちの支援にならない、と考えたことが伝わるかな、と思うのです。
私自身は、長崎の出身ではありません。九州からは遠く、北関東で育ち、東京の大学・大学院で学びました。
高校時代は、医学部に行きたくて踏ん張っていました。しかし、数学Iと化学が苦手で地を這うような成績、一方で国語や社会は得意でトップ、同じ理科でも物理と生物は好きでそこそこ、数学も数列はできる、という、なんだかよくわからないことになっていました。言語能力や語彙力、知識の獲得は得意だけれど、それに比して数的処理や空間認知の力が低いわけですから、今なら、ストーリー仕立ての学習教材をうまく生かせばいいとか、理屈で説明できないとわからないのですよ、とかアドバイスして、長所活用型の学習を取り入れたらどう?と伝えてあげられますし、「WISCとK-ABC※を受けてみたら?」と言ってあげたいような気もしますね。
※K-ABC Kaufman Assessment Battery for Children の略。子どもの知的能力を全般的な知能指数を知ることではなく、認知処理過程と知識・技能の習得度の両面から評価し、得意な認知処理様式を見つけ、それを子どもの指導・教育に活かすことを目的としています。
しかし、地方の高校生にそんなことがわかるわけはありませんし、今でもそうでしょうけれど、当時も数学と化学が苦手で受かる医学部なんてありませんでした。
医学部は、そもそも、重度の自閉症の妹とともに育ち、家族の苦悩を見聞きし、一方では素晴らしい支援者との出会いもあるなかで、私自身も精神科か小児科の医師になって自閉症の研究や臨床をしたいと思っての志望でした。
だったら、発達障害とその家族を支援できる心理士になろう!!と心機一転、文学部をめざしました。高校からは呆れられ、「医学部に失敗したからと言って文学部に行くやつはいない」、と非常に危惧されました。その危惧の通り、受験は失敗し、混迷を極めました。
私が「医学」に手が届かなかった瞬間でした。
数々の不合格の末、入学した東京の私立大学の文学部は、心理学・社会学の複合領域の学科でしたが、後日、研究の発想を広げる基礎となりましたし、自分の今を形作ったと考えています。何でもやってみないとわからないですね。それに、日本文学や東洋史、ドイツ文学は、現在まで私が心理面接をする基盤ともなっています。特にドイツ文学を学ばなかったら、フロイトやユングの精神はわからなかったでしょう。ですので文学部や大学に不満があったわけではなく、今でも愛する我らが母校なのですが、いかんせん、大学が大きすぎました。描いていたような子ども臨床の実践に、すぐにはたどり着くことはできませんでした。
障害児きょうだいは、過剰適応のあまり、親の期待を実際以上・必要以上に重く受け止めるものです。私も、医学部進学ができずに親の期待に沿えなかったけれど、いい報告をしたい、充実した大学生活を送らないと親に悪い、医学部じゃなくてもがんばってるといいたい!!と、苦悩もありました。
そんな状態を察した高校の恩師がそれを心配し、東京で心理士として働く知人を複数紹介してくださいました。そこからどんどんと輪が広がり、病院内の心理業務や、他大学のカウンセリングルームや相談室、区が実施している青年学級(障害のある成人の余暇活動グループ)、特殊学級(現在の特別支援学級)にボランティアや補助員として入ることができ、現場に積極的につながっていくことができ始めていきました。特に特別支援学級の子どもたちとは、通常授業のみならず、夏は海、秋は山、冬はスキーと、宿泊学習にも付いて行く中で、障害児理解や障害児指導法が何かを自分なりに考え、大学での知識と現場の経験を、往還させて学べるようになっていきました。何よりも子どもたちとの日々が楽しかった。
私の、「教育」との出会いでした。
学部卒業のころには、ちょうど指導を受けていた発達臨床心理学の教授が定年退職を迎えようとされていました。ある春の日、教授は、私の手あたり次第の活動を見て、「病院にも学校にも、福祉にも行政にも手を出して、それで何が一番楽しいの?これからどうしたい?」と聞いてきました。
どれも、勉強になるし、楽しいのです。そして、それぞれどこも、子どもにとっては必要な場所であり、支援なのです。しかし、私には、その間をつなぐものが、どうしても見出せませんでした。学校は学校で完結、病院はたまに学校と連絡を取るけれどまあそれぐらい。実感としては、毎日子どもたちにはあうけれど、私は毎日、違う場所で違うことをしている。そして卒業した子どもたちの居場所は、無理をして作らないと、むずかしい。学校にいるのは楽しいけれど、これでいいのかがわからない。こんな思いを吐き出してみたのです。
教授のアンサーの趣旨はこんなことだったと記憶しています。
「だったら、医療にも学校にも福祉にもどの領域にも入っていける心理士に、もしかしたらその全部をつなぐことができるかもしれない心理士になりなさい。行政の区分とか組織とか関係なく、フリーの立場で、手あたり次第でもいいから、いろいろな現場を見なさい。そこで何ができるか考えて、そこにいる人とともに考えて、それをかならず研究に、文章にしなさい。それが論文だよ。
ただし、現場で小器用にふるまうな。心理学は科学だということを絶対に忘れず、信頼性と妥当性のある研究を続ける研究者であり、臨床者であることを止めないこと。心理士は、将来性はないかもしれないけれど、現場を問わず、そして研究・臨床のどちらもつづけることができるし、そうでなければならないだろうから。心理学は、医学にも、教育学にも、必要だよ。」
今でも先生のこの言葉を、思い出します。
これが、私の「医教連携」の模索の始まりです。
大学院は、同じ大学内の教育学部の大学院に行きましたが、研究と並行して東京・埼玉・神奈川で発達障害の現場で働く場所をいただくことができました。教授の言った通り、非常勤で、手あたり次第です。いくつかの保健所の検診業務の心理相談員と育児相談員、病院の心理職、大学の教育相談室の相談員、学校の言語指導員、そして特別支援学級にはずっと補助員としておいてもらうことができました。研究と現場、いったりきたりです。
中でも、心理職として入った政令指定都市であるA市の総合病院では、地域支援と、児童精神科医を中心とした多職種のあり方を知りました。医学モデルで発達障害をどう考え、支援するのか。ほんとうの支援ニーズは何か。地域で包括的に支援するということ、行政がそのシステムを先導するということはどんなことなのか。
自閉症研究では最先端と言えるような病院であり、高名な先生方が多くおられましたので、勉強、研究も欠かさない。刺激的でした。地域における連携システムが確立しており、先生方を中心に包括的な支援を組み立てて地域支援に導入していくこと、もちろん学校にも母子保健にも積極的にでていくし、学校の立場を軽視することなく、子どもの学校での生活を念頭に置いて支援する。それを組織的に行うことを見て、ああ、これがやりたかったことかもしれない、と考えるようになったのです。
行政的なシステムを備えた「医教連携」の理想的なモデルを発見した、最初の経験です。
ところが突然、私は鹿児島の私立大学に着任することになりました。
システマティックな発達障害の支援体制が確立していた首都圏のA市に比べて、鹿児島はそれぞれががんばってはいるけれど、つながりはないようにみえました。でも私に見えないだけでA市に比べて遅れているというわけではないのです。A市モデルをそのまま導入もできないのです。地域支援は、地域の実情に合わせて作っていくしかないことに気が付きます。
一方で、地方都市ならではのいいこともありました。鹿児島は鹿児島市への人口一極集中、情報が集まりやすく、発信しやすい。そして地域の凝集性も高いのです。つまりは仲良くなりやすい。誰かが声を挙げれば、それがかたちになっていくのです。
そのうちに発達障害は、専門的な支援の必要性が叫ばれるようになり、発達障害に強い診療機関もどんどん増えました。そして、鹿児島市の保健所が中心になり行政主導の医療(機関となる病院)、福祉行政、学校教育、療育機関、福祉施設、保育機関、子育て支援施設、大学の相談施設等の実務者が集まり情報交換をする会議体が始まりました。ネットワーカーは、“長”ではなくて実務家が出席すること、年に複数回開催することにより、より有機的なネットワークが構築されました。これは、現在でいう発達障害者支援法に定められた発達障害者支援地域協議会のはしりでもありますね。
地域の実情に合わせた、新たな「医教連携」のはじまりです。
また、地方では国立大学を中心とした教員養成が確立していて、県内出身者の県内での教員就職率も高い。つまり、教員養成のなかで発達障害の知識と支援をしっかり学べば、学校現場は徐々に・確実に変わっていきます。これは、いくつかの私立大学を中心とする保育者養成や臨床心理士養成も同じでした。丁寧な支援者養成は、現場を変える近道です。
そして同時に、困っている現場へのアウトリーチ(専門家が学校や保育園に巡回し訪問し、コンサルテーションを行うことで、組織や子どもへの具体的な支援方法を提案すること)は非常に有効でした。学校や幼稚園・保育園、児童養護施設、療育施設、子育て支援施設、保健所などに入らせていただく経験は、東京時代と同じでした。異なるのは、東京時代には自分が現場に入り込んで、その専門職の一員として、心理士として働いていたけれど、鹿児島では、コーディネーターやコンサルテーション、システムづくりに徹したことです。
年に200件近いアウトリーチを続けるうちに、教員養成と、教員研修における発達障害教育の充実は、現場を変える最短の道だと確信できるようになります。鹿児島での16年間は、こうした現場での学びと大学での支援者養成となっていきました。
こうして私のなかの「医教連携」に、支援者養成(教員・保育者など)が加わったのです。
そして長崎に来ました。長崎大学では教員養成学部である、教育学部に着任しました。そして、まだ長崎の様子が十分に掴みきれていない、県内のネットワークに自分は十分に関与していないときの、佐世保の事件でした。
長崎大学ではこの件を考えるワーキンググループを立ち上げて検討を重ねました。
長崎に何が足りなかったのか。私たちの出した結論は、戦犯探しではなく、一人ひとりの、ほんの小さな躊躇。その躊躇が解決されず共有されないまま、蓄積したのではないか。私たちは、十分につながりあっていなかった。今、教育現場はとても怖がっている。このままではいけない。
実はこのワーキンググループを開いてみて、実は長崎には発達障害を専門とする研究者は、長崎大学の中でもたくさん存在していたことに気が付きます。そして地域にも、発達障害を診療できる優秀な医療機関が、この地方都市の規模からみると驚くほどたくさんありました。
しかし、それが十分につながっていなかった。私だって、たくさんの現場とかかわってきながら、自分だけの動きであって、有機的なネットワーカーにはなっていなかった。
今度はひとりではありません。大学内に、仲間がたくさんいます。できることはたくさんあります。このみんなの思いが、子どもの心の医療教育センターの立ち上げにつながっていきました。
そして、大学という教育機関の役割として、医学科は医師の養成を、大学病院は思春期専門の医師を。保健学科は看護師・作業療法士・理学療法士という支援者養成を、教育学部は教員養成・保育者養成をと、支援者養成に取り組んでいるわけですから、その養成の段階で、支援者が持つ『共通言語』をつくろう。
その『共通言語』を持つために、どの学部も選択できる、発達障害について学べる科目をつくろう。精神医学・保健学・心理学・生理学・教育学・社会福祉学等の専門家の知見を活かした、学際的な視点を持った科目を作ろう。
こうして、「私の勝手な医教連携」の歴史は幕を閉じました。
書いてみて気が付きましたが、こんなに美しいお話ではなかったです。苦しいことも失敗もたくさんありました。
前回にお話しした、「大学としての医教連携」の取り組みが始まりました。その中で、支援者養成の授業科目をつくるために動き始めます。
◆吉田 ゆり(よしだ ゆり)
長崎大学教育学部・教育学研究科 教授。専門は発達臨床心理学。公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士、そして保育士でもある。
■□ あとがき ■□--------------------------
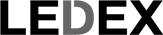

 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら